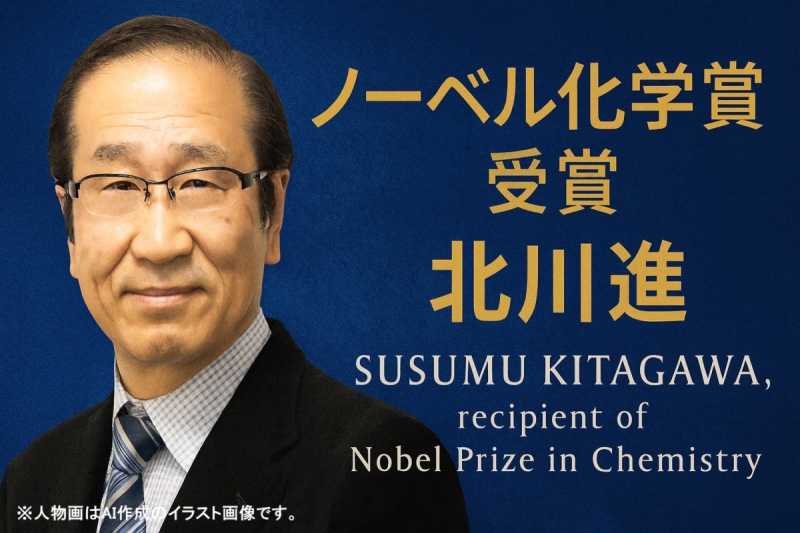2025年10月8日、京都大学・北川進特別教授が、リチャード・ロブソン、オマー・ヤギー両氏とともにノーベル化学賞を受賞した。受賞理由は「金属有機構造体(MOF/多孔性配位高分子=PCP)の開発」である。金属イオンと有機配位子を組み合わせ、ナノサイズの孔を規則正しく配列させる“超多孔”材料群は、二酸化炭素回収やガス貯蔵、水資源獲得など、環境・エネルギー課題を横断する基盤技術として世界を動かし始めた。スウェーデン王立科学アカデミーは「化学者たちは数万種のMOFを設計し、化学の新たな驚異を切り拓いた」と記す。京都大学も「研究推進担当理事ならびに特別教授としての受賞」を伝え、iCeMS(アイセムス)は「人類の未来に深い影響を与えるブレークスルー」と讃えた。[出典:NobelPrize.org、京都大学・iCeMS ]
ZEROICHIはこの受賞を“速報としての称賛”で終わらせない。なぜなら、我々は2021年に堀江貴文編集長が北川氏と樋口雅一氏(当時・京大特定助教、Atomis創業者)を集中取材し、PCP/MOFの原理と社会実装の可能性を連続記事で掘り下げてきたからである。本特集は、その取材記事を素材に「引用」というかたちで再構成し、今回の受賞を機に“何が新しく、どこまで来たのか”を編集部視点で読み解くものである。以下、見出しごとに要点を整理する。
1|“混ぜるだけ”で新物質、そして孔が生まれた
北川氏はPCP/MOFの起源を、驚くほど平易な言葉で説明している。「PCPの作り方は実に簡単で、金属イオンと有機配位子を混ぜるだけ」(2021年取材)。無機と有機をナノスケールで組み合わせると、単なる混合物ではない“金属錯体”が形成され、その内部にナノサイズの孔が規則正しく空く。このシンプルさと構造的な緻密さの同居が、MOFの本質である。
重要なのは「見える化」だ。1990年代後半、微小結晶の構造解析がラボ単位で可能になったことで、“そこにある孔”を設計して使う発想が現実味を帯びた。MOFは“複雑な合成”よりも“複雑な設計”にアイデンティティがある。孔のサイズ、形、表面の化学性を自在に“描く”ことで、吸着・分離・触媒・輸送といった機能が立ち上がる。
2|鍵はファンデルワールス力—「入れやすく、出しやすい」気体の運命
2021年の対話で、北川氏は分子を孔に“出し入れ”する駆動力をこう説いた。「ナノメートルまで近づくと“弱い引力”が働く。孔が分子サイズに合えば“引っ張られて埋め込まれる”。弱い力だから、『ちょっと加熱』や『ちょっと減圧』で出せる」。強固な化学結合ではなく、弱い相互作用を使うからこそ、低エネルギーで可逆的な吸着・放出ができる。MOFの“使い勝手”はここにある。
研究段階では、従来法に比べ低負荷での実現を目指す成果が相次いで報告されている。ノーベル委員会の解説も、CO₂やH₂の貯蔵、水の回収などへの適用を具体例として挙げる。[出典:NobelPrize.org ]
3|「スポンジ」と「バルブ」—安全・物流・運用のリアリティ
堀江編集長が「低圧容器の中に水を含んだスポンジが入っている」とたとえると、北川氏は「その比喩で構わない」と応じた。MOFの孔にガスを充填し、バルブを開けば圧力差で放出できる。高圧シリンダーに比べて低〜中圧域を狙う設計思想で、安全性と取り扱いやすさを両立させる構想だ。“極厚の鋼製シリンダー+超高圧”という従来の定理を条件緩和できれば、安全性・軽量化・現場運用の設計クォリティが一段上がる。
樋口氏が手掛けた次世代ガス容器「CubiTan」の構想(MOF搭載・IoT監視)も、その延長線上にある。“どこで、どれだけ、何を運ぶか”をデータで回す。材料科学がロジスティクスと接続する時代の入口だ。
4|「Hermioneのバッグ」から宇宙船まで—用途は“孔の設計力”次第
一部メディアでは、MOFを“ハーマイオニーのハンドバッグ”になぞらえる表現も用いられた。小さな体積に巨大な内部空間—比表面積の極限は、CO₂捕集、水素貯蔵、砂漠空気からの飲料水回収、有害物質除去(PFAS等)まで、ユースケースを急拡大させた。ノーベル財団のページも同趣旨だ。[出典:The Guardian、AP News ]
ZEROICHIの取材でも、宇宙船内のCO₂コントロールという話題が交わされた。有人環境ではCO₂濃度が上昇すると集中力や判断力の低下を招くとされ、ISSなどでは2,500ppm前後を運用上限とする。一方、5,000ppmは労働安全衛生上の許容濃度とされる。従来は活性炭やゼオライトが主役だったが、MOFは選択性と可逆性で新機軸を提示できる。“捨てていた炭素資源を、回収し、変換し、再利用する”という循環発想は、宇宙と地上をつなぐ。
5|バイオメタンから医療へ—“選んで通す/選んで抱く”二つの流儀
北海道の酪農由来メタンの話も印象的だ。不純物が多い原ガスから“いらない分子だけを捕まえる”か、逆に“欲しい分子だけを抱え込む”か。樋口氏は「硫黄系など“強くくっつく”不純物をMOFで先に取る方が実装に近い」と語った。分離と精製は、現場の運転条件とコストで最適解が変わる。MOFは“孔の化学性を描き替える”ことで、選択の自由度を確保する。
さらに、“食べられる元素”(Ca・Fe・Mg)×安全な有機物で構成した“バイオMOF”という展開も紹介された。ドラッグデリバリーや免疫誘導のプラットフォーム候補として、医療と材料の境界に新領域がひらける。“孔の工学”が生命に触れる。これもMOF時代の特徴である。
6|「理論から社会実装へ」—“設計—製造—運用”を結ぶ産学連携
今回の受賞は、「構造を創る化学」の決定打としての授賞であると同時に、社会実装の成熟に対する評価でもある。ノーベル財団の“Popular information”は、“数万種のMOF”という広がりと、CO₂・H₂・水分子など具体的な対象に触れている。学術の多様性×産業の多様性が、“孔”という共通語で噛み合い始めた。[出典:NobelPrize.org ]
ZEROICHIの取材が浮き彫りにしたのは、研究—起業—現場が一体となって“材料を社会で運転する”視点である。MOF搭載容器のIoT化、ガス物流の最適化、プラントや宇宙機の運用要求への適合。材料単独では価値にならない。装置・システム・規制・市場をまたぐ編集が、価値を束ねる。
7|「PCP/MOFが変える“圧力”の常識」—編集部の注目点
- “高圧の呪縛”からの解放
MOFにより必要圧力の最適化が進む。安全率の再設計、容器の軽量化、据付・保全コストの削減。エネルギーを“運ぶ”産業の損益分岐点が動く。 - “分離は新しい発電”という感覚
分離・精製工程の省エネ化は、実質的な創エネに等しい。化学プロセスのCO₂原単位を直接下げる“静かな革命”の主役になりうる。 - “水を空気から”の現実味
砂漠空気からの吸着—放出サイクルは、熱源や再エネ電力とのハイブリッドで分散型水資源をつくる。気候レジリエンスの新手筋だ。[出典:The Guardian ] - “材料×ロジスティクス×データ”の統合
MOF容器+IoT+SaaSで、ガスサプライチェーンが可視化される。需要予測・回収・再充填を含む循環最適化は、地域エネルギーや農業由来メタンにも効く。 - “医療としての孔”
バイオMOFは、デリバリー×免疫の二正面で成熟が進む。小分子・ガス・生体分子という対象の拡張が、規制科学と共鳴するフェーズに入った。
8|編集長取材の射程—「世界は孔で編み直せるか」
2021年、堀江編集長は「スポンジ」「バルブ」「宇宙船」「バイオメタン」「CubiTan」という運用の言葉でPCP/MOFを問い、北川・樋口両氏は物理化学の言葉で応答した。学術と言語、産業と言語の橋がかかったとき、“材料”は社会のインフラに変わる。我々は、その瞬間を記録していた。
そして2025年、ノーベル賞という歴史のハイライトが灯った。だが、これは終止符ではない。CO₂削減の速度、エネルギー安全保障、資源循環、水ストレス。どれも分子スケールの設計力なくしては解けない。PCP/MOFは“孔”で世界をつなぎ直す技術である。“弱い力”を束ね、強い社会をつくるという逆説に、次の10年の希望がある。
9|引用(素材)—ZEROICHI過去記事より
- 「PCPの作り方は実に簡単で、金属イオンと有機配位子を混ぜるだけ」(北川進、2021/09/09公開インタビューより)
- 「弱い引力(ファンデルワールス力)で分子サイズが合う孔に埋め込み、少しの加熱・減圧で出す」(北川進、同上)
- 「低圧容器の“スポンジ”の比喩」「宇宙船のCO₂管理」「北海道のバイオメタン」(堀江—北川対話、2021/09/10公開インタビューより)
- 「硫黄系不純物を先に捕まえる分離戦略」「MOF搭載容器CubiTanとIoT監視」(樋口雅一、同上)
※引用は文脈上の要約を含む。原文は以下。
「特定の気体を孔に吸蔵させて運べる」—PCPとは?その1(2021.09.09)
https://zeroichi.media/with/920
「牛から出たメタンガスでロケットが飛ぶ!?」—PCPとは?その2(2021.09.10)
https://zeroichi.media/with/923
10|受賞情報(参考)
- ノーベル化学賞2025 受賞者:北川進、リチャード・ロブソン、オマー・ヤギー
授賞理由:「金属有機構造体(MOF)の開発」🔗NobelPrize.org - Popular information(NobelPrize.org):MOFの意義と応用の平易な解説。🔗NobelPrize.org
- 京都大学・公式発表、iCeMS発表:受賞の報告とメッセージ。🔗京都大学・iCeMS
編集部・注目理由(ZEROICHI)
- “分子設計=社会設計”の証左
MOFは材料—装置—制度—運用を一続きに結び、技術と社会を往復させる。孔は“新しい公共インフラの単位”である。 - 現場実装の速度
CO₂回収・分離、ガス物流、水回収、医療など、規制・市場・電力系統が異なる複数領域で並行的に前進している。“横展開可能なプラットフォーム”の強みが際立つ。 - 日本発のストーリー
北川氏(京都)—ヤギー氏(米)—ロブソン氏(豪)という国際連携の原点に、日本の大学・企業・スタートアップが再び接続し直せる可能性がある。
最後に。北川進氏の言葉を借りれば、PCP/MOFは「孔を使おう」という発想の革命である。“そこに在る”孔を“使える”孔に変える。この小さな転回が、地球スケールの課題に通じる。受賞は、その道のりの“節”にすぎない。ZEROICHIは、“孔が社会を動かす”瞬間をこれからも追い続ける。
※本記事は、原文から一部編集・要約して掲載しています。本稿は研究動向・技術概説であり、特定用途での性能・安全・適合性を保証するものではありません。